「素心(そしん)」と「美点凝視(びてんぎょうし)」は、月刊誌『致知』やその関連する人間学的な教育・実践活動(たとえば木鶏会)において非常に重要なキーワードです。それぞれ、自己を見つめる姿勢と他者を見るまなざしに深く関わっています。以下、できるだけ具体的かつ実践的に詳しく説明します。
🌿「素心(そしん)」とは
■ 意味と語源
「素心」とは、文字通り「素(す)の心」、つまり飾らず、まっすぐで、純粋な心を指します。打算や虚飾のない、本来の自然な心の状態であり、東洋思想、とりわけ儒教や陽明学で重視される「誠」や「良知」と通じる概念です。
■ 解説・背景
-
「素心」は“求めない心”でもある
たとえば名誉や利益、外的な評価を追い求めすぎると、人は迷いや不安に飲み込まれます。素心はそのような欲望を一旦手放し、「ただあるがままの自分」と向き合う姿勢です。
-
老子や荘子、孔子の思想と重なる
道教では「無為自然」、儒教では「仁」や「中庸」の考えに近く、「何が正しいか」「自分の心に正直であるか」が常に問われるのです。
■ 具体的な実践例
-
利害で動かない行動をとる
たとえば職場での判断において、評価や得失よりも「自分が本当に正しいと思うこと」を基準にする。
-
心を整える習慣を持つ
毎朝、感謝や誓いの言葉を自分に問いかける。例:「私は今日一日、誠を尽くして生きる」「心に一点の曇りもなく進もう」
-
他者の評価に振り回されない
SNSや周囲の声に過度に反応せず、自分が大切にする価値観に基づいて行動する。
■ 素心の人の特徴
-
落ち着いている
-
道徳的・誠実
-
他人と比較しない
-
失敗を引きずらない
-
誰の前でも同じ態度をとれる
👁「美点凝視(びてんぎょうし)」とは
■ 意味
「美点凝視」とは、他人の長所(=美点)に焦点を当てて、そこを深く見つめる姿勢を指します。欠点や過ちよりも、その人の持つ“良さ”に注目することで、信頼と成長の土台を築くという考えです。
■ 背景
この言葉は教育者・森信三氏やPHP創設者の松下幸之助氏にも通じる「人間観」に基づきます。すなわち、人は“伸びる可能性”を持っており、それを信じるまなざしが必要だという思想です。
■ 美点凝視の実践例
-
部下や子どもの「いいところ」を紙に書き出す
どんなに些細なことであっても、「真面目に出勤している」「声が元気」など、ポジティブな面を見つけてノートに残す。
-
会議や対話で褒め言葉を先に言う
「君のアイデア、すごく面白いね」とまず肯定した上で建設的なフィードバックを行う。
-
意図的に“批判しない日”を作る
一日だけ、家族・同僚・店員などに対して、批判・不満を口に出さず、美点だけを見る訓練。
-
“長所は裏返せば短所”を理解する
例:頑固=信念がある/おっとり=落ち着きがある/口数が少ない=傾聴力がある
■ 組織・チームにおける効用
-
信頼関係が築かれやすくなる
-
自信を持てる人が増える
-
フィードバックがポジティブになる
-
雰囲気が明るくなる
-
離職率の低下にもつながる
✨「素心」と「美点凝視」を同時に持つということ
「素心」は自分を見る心の姿勢、「美点凝視」は他者を見る目の姿勢です。この2つを併せ持つことが、真にバランスの取れた人格形成につながるとされています。
|
視点 |
姿勢 |
意味 |
実践テーマ |
|---|---|---|---|
|
自分に対して |
素心 |
素直で私欲のない心 |
誠を尽くす、ぶれない自己軸 |
|
他人に対して |
美点凝視 |
長所を見て信じる眼差し |
信頼を築く、他者を伸ばす |
🧘♀️ 木鶏会や人間学でどう活かされているか
『致知』を使った木鶏会では、素心・美点凝視の実践が核となっています。
-
素心:記事を読む際に「自分がどう感じたか」「本心で何を思ったか」を言語化し、表面的な発言を避ける。
-
美点凝視:他人の感想を聞くときには、「ここがすばらしい」「この視点が新鮮」と肯定的に受け止める。
この相互作用が、安心できる学びの空間をつくり出し、参加者の内面成長につながっています。
🧠 まとめ:現代における意義
現代は、情報過多・他者評価主義・成果至上主義に傾きがちな時代です。そんな時こそ、「素心=本当の自分」「美点凝視=信頼のまなざし」という2つの軸は、自分を見失わず、他者とよい関係を築く羅針盤となるのです。
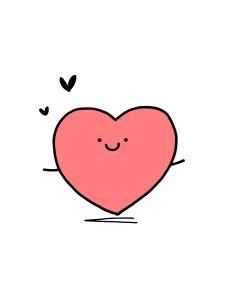





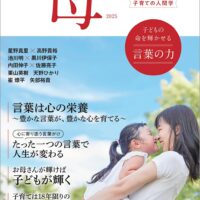
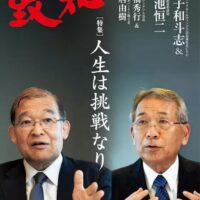







この記事へのコメントはありません。